

しかし、今になって改めて歌詞や大事に保存している当時の月刊誌を読んでみて、そこには皮肉や風刺が効いた曲がたくさんあることに気づきました。

この記事では、ビートルズの名曲に隠された皮肉や風刺について、私自身の解釈を交えながら紹介していきます。内容は、結構面白いですよ。
尚、各曲紹介の頭には、ビートルズのYouTubeオフィシャルサイトが発行するコードを貼って、それぞれの曲を聞けるようにしています。
目 次
Day Tripper – 一時的な関心に対する皮肉
「Day Tripper」は、ポール・マッカートニーによる1965年の曲です。
片道切符しか持たない旅行者や、彼氏の気持ちを無視した一夜の関係しか望まない女性を歌っています。
しかし、これを通してポールが本当に伝えたかったのは、一時的な興味や関心だけで、決して深いところまで知る努力をせず、軽薄な態度を取る人たちへの皮肉です。
ポイントになるフレーズ
1.”She was a day tripper / A one way ticket, yeah”
このフレーズは、主人公が一つのことに興味が続かない事を意味しています。
だから”one way ticket“しか持たなくて、また別の世界に行くのです。
これは、大きな1960年代の社会変革の中で、多くの人々が表面的な参加や関心を持つ一方で、真剣な関与を避けている状況を風刺しています。
2.”Tried to please her / She only played one night stands”
このフレーズは、彼氏が彼女を喜ばせようとするものの、彼女は一夜限りの関係しか求めないことを示しています。
これも、一時的な関心や関与しか持たない人々の軽薄な態度を象徴しています。
主語の省略形
英語の歌詞や詩では、リズムや韻を合わせるために主語が省略されることがよくあります。
出だしの”Got a good reason“ですが、文法的には”She has got a good reason“です。
間奏後の出だしも同様に主語が省略されています。
“Tried to please he“ですね。これは”He“を省略した形で、正確には”He tried to please her“です。
この曲が流行っていたときは中学生で、そんな事考えもしなかった。完全に乗りで歌っていたし、学生だから表面的な意味はある程度わかったにしても、そもそもそういう方面にウエイトが乗ってなかった。
1960年代の表面的な関心の背景
“Day Tripper“が作られた1965年は、1960年代の中でも特に大きな社会変革が進行していた時期です。
1960年代の多くの人々が表面的な関心を持つに至った背景には、いくつかの社会的、文化的な要因があり、これらを掘り下げることで、当時の状況をより深く理解できます。
1. メディアの影響力の増大
1960年代はテレビの普及が急速に進み、大衆文化が大きく変わりました。
テレビは情報を迅速かつ広範囲に伝えるメディアとして、多くの人々に新しいライフスタイルや流行を紹介しました。
しかし、短時間で多くの情報が伝えられるため、深い理解や分析が不足し、表面的な興味に終始することが多くなりました。
2. 消費文化の拡大
戦後の経済成長により、消費文化が急速に拡大しました。
人々は新しい製品やファッション、エンターテイメントに強い関心を持つようになり、それらを手に入れることが幸福の象徴とされました。
しかし、消費文化は一時的な満足感を追求する傾向があり、結果として、持続的な関心や深い関与を妨げることもありました。物を買うほど虚しさを覚える・・みたいな。
3. 社会運動の多様化と疲労感
1960年代は公民権運動、反戦運動、フェミニズム運動など、多くの社会運動が同時に進行しました。
これにより、多くの人々が様々な問題に対する関心を持ちましたが、運動が多様化するにつれ、個々の運動に対する関与が分散し、表面的な参加にとどまることが増えました。
また、社会運動の激化と持続により、多くの人々が疲労感を感じ、深い関与を避けるようになりました。
4. カウンターカルチャーの影響
カウンターカルチャー運動は、既存の社会規範に対する反発として生まれましたが、その一部は反抗すること自体が目的となり、深い思索や持続的な行動を伴わない表面的な行動が目立つようになりました。
一部の若者は、反体制的なスタイルや一時的な行動に走り、実質的な変革を追求しない事も多々ありました。
Eleanor Rigby – 孤独感と疎外感
この曲はキリスト教文化に根ざした内容が含まれているため、日本人にはわかりにくい面があるかもしれません。
しかし、その一方で、曲が示唆するテーマは戦後の世界全体に通じるものであり、日本人にも共感できる要素が含まれています。
孤独の描写
“Eleanor Rigby“は、孤独な人々の生活を詳細に描写しています。
エリナー・リグビーという架空の人物と、彼女が埋葬された教会の架空の神父マッケンジーの視点から、現代社会における孤独感と疎外感を浮き彫りにしています。
歴史的背景
この曲が発表された1966年は、第二次世界大戦後のベビーブーム世代が成長し、都市化と核家族化が進行していた時代です。
人々は以前のような共同体の一員としての結びつきを失い、都市部での個別化した生活が増加しました。
こういった背景が、個人の孤独感や疎外感を一層強める要因となりました。
ポイントになるフレーズと深い考察
1. “All the lonely people / Where do they all come from?”
このフレーズは、孤独な人々がどこから来るのか、なぜこんなに多くの人々が孤独を感じるのかを問いかけています。
この問いは、現代社会の構造的な問題を反映しています。
エリナー・リグビーの死に誰も気づかず、葬儀に誰も参列しない描写は、社会がいかに個人の孤独に無関心であるかを示しています。
これは、現代社会の冷淡さや人間関係の希薄化を批判するものと捉えることができます。
ポールは、エリナー・リグビーの孤独を通じて、都市化と個別化が進む現代社会の暗い一面を浮き彫りにしています。
2. “Father McKenzie / Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave“
このフレーズは、神父がエリナー・リグビーの葬儀を、ごく形式的に終えたことを示しています。
彼の行動が儀式的であり、感情が伴っていないことを強調してるんですね。
神父自身もまた孤独であり、彼の儀式はとても生気を欠いています。
この描写は、宗教的な儀式が形式的であり、人々の心に届いていないことを風刺しています。
もっと言えば、信仰が本来持つべき精神的な支えの役割が果たされていない現実を批判しているのです。
現代への問いかけ
“Eleanor Rigby“は、1960年代の社会背景を反映しつつ、現代社会に対する普遍的な問いかけを含んでいます。
都市化と個別化が進む中で、人々がどのように孤独を感じ、その孤独をどのように解消するかという問題は、今日でも依然として重要なテーマです。
**
“Eleanor Rigby“は、孤独感と疎外感を強く描写していますが、この記事のテーマである皮肉や風刺を直接的に含むわけではありません。
ただし、社会の無関心や宗教の形式主義に対する間接的な批判として解釈することはできるでしょう。
この曲は、現代社会の人間関係の脆弱さや孤独感を鋭く描写し、聞き手に深い考察を促すものです。
また、1960年代の都市化と個別化の進行という歴史的背景を考慮することで、この曲のメッセージがさらに深まります。
Taxman – 政府と税制度への批判
この曲は今回この記事に収録した中で最高に強烈な曲です。
ビートルズの曲は、この記事で解説するように、詩の中に皮肉や風刺を織り込むケースが多くあるのですが、”Taxman“はダイレクトな文句メッセージですからね。超異質です。
しかも、当時の現役の政府首脳に名指しで「お前らええかげんにせえよ」と歌っており笑います。
いや〜勇気がありますね。
さて、”Taxman“は、ジョージ・ハリスンが1966年に発表した曲で、高額な税金に対する直接的な批判を歌っています。
この曲は、ビートルズが税金の負担に悩まされていたことから生まれました。
当時のイギリスでは、高額所得者に対する課税が非常に厳しく、ビートルズの収入のほとんどが税金として徴収されていました。
歴史的背景
1960年代のイギリスでは、労働党政府が高所得者に対する重税政策を実施していました(超重税)。
このため、多くの芸術家や高収入の人々が重税に苦しんでいました。
ジョージ・ハリスンはこの状況に強い不満を抱き、”Taxman“を通じて政府の課税政策を鋭く批判しました。
高額課税と「ブレイン・ドレイン」
1960年代後半、イギリスの労働党政府は高額所得者に対する重税政策を実施していました。
特に、所得税の最高税率が90%以上に達することもありました。
このため、多くの高所得者が税金の負担に耐えられず、国外に移住することを選びました。
この重税政策により、多くの著名なミュージシャン、俳優、作家、学者などがイギリスを離れました。
ビートルズのメンバーもその一部であり、特にジョージ・ハリスンはこの状況に強い不満を抱いていました。”Taxman“は、その不満をダイレクトに表現した曲です。
エピソード
ビートルズと並んで有名なバンドであるローリング・ストーンズも、税金の負担から逃れるためにフランスに移住しました。
彼らのアルバム「Exile on Main St.」は、この国外移住の間に録音されたものです。
著名な映画監督であるリチャード・アッテンボローも、重税政策に対する不満から一時的に国外に移住しました。
ポイントになるフレーズと深い考察
1. “If you drive a car, I’ll tax the street / If you try to sit, I’ll tax your seat”
このフレーズは、政府がどこにでも税金を課すことを風刺しています。
車を運転すれば道路に税金がかかり、座れば椅子に税金がかかるという表現は、課税が過度であることを強調しています。
ジョージの不満と批判が直接的に表現されており、多くの人々の共感を呼びました。
2. “Don’t ask me what I want it for / If you don’t want to pay some more”
このフレーズは、政府がどのように税金を使うかについて説明責任を果たさず、さらに多くの税金を要求することを批判しています。
これは、税金の使い道についての透明性が欠如していることを強調しており、政府の不透明な運営に対する不満を表しています。
3. “There’s one for you, nineteen for me / ‘Cause I’m the taxman”
このフレーズは、ジョージ・ハリスンが具体的な数字を使って税金の負担の大きさを示しています。
「君に1、僕に19」と、自分の取り分がいかに少なく、政府にバカみたいに多く取られているかを強調しています。
ただ、少しわかりにくいのは、ジョージが人称倒置を使っており、わざと政府と自分を逆さまに表現しています。
この表現法は、皮肉を強調するための手法です。ジョージ・ハリスンは、税金が非常に高く、自分の手元にほとんど何も残らない状況を逆説的に表現しているのです。
何度も言いますが、ジョージの怒り度が如何にマックスであったことがよくわかります。
遂に政府関係者への切り込み
ジョージは「Taxman」で、遂に特定の政府関係者にまで切り込んでいます。
“Taxman, Mr. Wilson / Taxman, Mr. Heath”
↑見てください。なんとダイレクトに政府高官の名前を歌詞に入れてますよ。
当時のイギリス首相ハロルド・ウィルソンと保守党のリーダーであるエドワード・ヒースの二人です。
ジョージは、曲の中で彼らの名前を直接挙げ、政府の課税政策を皮肉っています。よほど腹に据えかねていたのだと推察されます。
リスナーに対して政府の責任者を明確に指摘し、批判の矛先を明らかにしたかったんでしょうね。
この曲は、もう単なる音楽作品を超えて、社会的・政治的なダイレクト・メッセージ・ソングとして強く発信されている曲です。
因みに、この歌詞が正しい数値を歌っているとしたら、ジョージにかかっていた税率は
19/20=0.95
つまり95%になります。そらジョージも怒るわなぁ。
(豆知識):当時のイギリスの最高税率は約83%でした。ところがその上にサーチャージなるものが乗ることが有りまして、これを加算すると最高税率は実質98%にまで達したそうです。
「Taxman」の適切な和訳は?
通常は、税務署の職員というような意味ですが、この曲のメッセージ性を鑑みると
「税金泥棒」
くらいが適訳かと思います。
Back in the U.S.S.R. – ビーチボーイズとソ連
「Back in the U.S.S.R.」は、ポール・マッカートニーが書いたノリの良い8ビートのロックンロールで、1968年の”The White Album“に収録されています。
この曲の面白いところは、わざとアメリカンなサウンドで冷戦時代のソ連を歌い、両大国に対して皮肉をかましているところです。
リンゴ・スターが一時離脱したので、ドラムはポール・マッカートニーが担当しました。メンバー間に不穏な空気が流れ出した時期でもありました。
「Back in the U.S.S.R.」の歌詞を理解するための大前提。
先に結論を述べますと、ポールはこの曲で二つの大国のプロパガンダを皮肉っています。
当時は冷戦時代で、アメリカもソ連も互いに自国の優位性を盛んにプロパガンダ合戦していました。
アメリカは自由と豊かさを強調するプロモーションを、ソ連は社会主義の成功や労働者の楽園としてのプロモーションを行っていたのです。
ポールは両方とも皮肉って虚しいもんだと訴えています。
しかし、とてもややこしいのは、素直にまっすぐに訴えず、わざとアメリカンロックンロールスタイルを使って、ビーチボーイズの歌詞を真似て、つまりアメリカ色の音楽でもって、表面上の歌詞はソ連を称賛していることです。
こういう複雑な手法を使ったので、誤解され、発表当時は右派左派の両方から相当批判されました。
Back in the U.S.S.R.はCalifornia Girlsのパロディ?
少し上でも触れましたが、、、
この曲は、アメリカのロックンロールスタイルを用い、ビーチボーイズの”California Girls“をパロディにしたスタイルが特徴です。
音楽的にはビーチボーイズはあんまり関係なく、あえて言えば、アメリカンロックンロールがそれらしいと言えばそうかもしれません。
しかし、歌詞は明らかにビーチ・ボーイズのCalifornia Girlsを意識しています。
- ビーチボーイズ:主に西海岸(歌詞の一部には東海岸も)の女の子たちがオシャレで好きだみたいな事を歌っている。
- ポール:強烈なアメリカンロックンロールでロシアのモスクワ・ウクライナ・ジョージアの女性を賛美している。
実際の歌詞で比較してみましょうか。
- California Girls:“Well, East coast girls are hip, I really dig those styles they wear”
- Back in the U.S.S.R.:“Well the Ukraine girls really knock me out, they leave the West behind”
“they leave the West behind”
直訳すると、「彼らは西(の人たち)を後ろに置き去りにする」ですが、それだと意味が全く理解できません。
適切な訳は「ウクライナの女の子たちは西側の女の子たちを凌駕している」くらいであり、これだと言いたいことがよく分かるでしょう。
先に説明した通り、これはあくまでも表向きの意味です。ポールが本当に伝えたかった事は裏側に秘められています。
ポイントになるフレーズと深い考察
1.”Back in the U.S.S.R. / You don’t know how lucky you are, boy”
このフレーズは、アメリカンロックンロールの表現を使いながら、ソビエト連邦での生活がいかに良いかを歌ってますが、これは皮肉です。
冷戦時代の政治的緊張を背景に、両国のプロパガンダを風刺しています。
つまり、ポールはアメリカンロックンロールのスタイルを借りて、ソ連での生活を称賛するように見せかけ、その実、アメリカとソ連の両国のプロパガンダの虚しさを浮き彫りにしています。
2.”Show me round your snow-peaked mountains way down south / Take me to your daddy’s farm”
前半は「南にある雪に覆われた山々を案内してくれ」、後半は「君の父さんの農場に連れて行ってくれ」。両方ともソ連での描写です。
このフレーズは、ソ連の地理的および文化的多様性を称賛し、アメリカの田舎風景と対比させています。
ポールは、ソ連が持つ自然の美しさ(歌詞に出てくる風景はおそらくカフカス山脈のような美しい雪に覆われた山々だと推測)や農村生活の魅力を強調し、アメリカの同様のイメージをパロディ化しています。
例えば”daddy’s farm“という言い方は、アメリカのカントリーミュージックによく出てくる表現で、ポールは恐らくわざと使っています。
いずれにしても、冷戦時代の両国が互いに自国の優位性を誇示するプロパガンダに対して、ポールは批判をしたかったのでしょうね。
それにしてもなんでこんなにややこしい誤解されやすい表現方法を取ったのでしょうね。
社会的背景と影響
繰り返しになりますが、、、
この曲は、冷戦時代の緊張とプロパガンダを背景にしており、ビートルズの楽曲の中でも特に政治的な意図が強いものです。
アメリカとソ連の両国が互いに相手を敵視し、自国の優位性を誇示するプロパガンダを繰り広げていた時代に、マッカートニーはその両方を皮肉っています。
自由主義国の右派からも左派からも批判を受ける
この曲はそのリリース当時、自由主義国の右派および一部の左派からも批判を受けました。
右派からの批判
自由主義国の右派勢力は、冷戦時代のソ連に対して強い反感を持っていました。
彼らは、ビートルズがこの曲でソ連を称賛していると解釈し、激しく非難しました。
この曲がソ連の生活を称賛するように見える部分が、彼らの反感を招いたのです。
- 「アメリカや西側諸国の価値観を否定している」
- 「ソ連を支持している」との誤解
左派からの批判
一部の左派は、ビートルズがこの曲でソ連を揶揄し、冷戦時代の緊張を煽っていると感じました。
特に、ソ連を皮肉ることで、彼らが理想とする共産主義や社会主義のイメージが損なわれると考えたのです。
- 「共産主義や社会主義の理想を侮辱している」
- 「冷戦の緊張を助長している」
Happiness is a Warm Gun – ラリった頭で銃社会を批判
“Happiness is a Warm Gun“はジョン・レノンがビートルズの1968年のアルバム”The White Album“に収録した曲です。
その複雑なテーマと大胆な表現が特徴の曲であり、アメリカの銃文化やセクシュアルな暗喩、ドラッグの影響など、様々な要素が含まれています。
ビートルズの213曲の中でも極め付きのややこしい曲で、きっちりBBCなどからバンを食らってます。
**
この記事は、ビートルズの曲が内に秘めている皮肉や風刺や批判の解説が主目的ですが、この曲に関しては、音楽としてあまりにも変わっているので、少し「曲」そのものの解説もします。
ビートルズ一番の複雑怪奇な曲
以下に説明しているように幾つかの詩と曲が合体したような構成ですが、くるくる変わる場面の話としての連続性はなく、しかもそれぞれの話も内容がよくわからない。
音楽としては拍子がえらい複雑で、4/4と3/4が入れ替わり立ち替わりで、しかも、その間に2/4、5/4、9/8、12/8、9/8などが混ざっています。
これだけ複雑になると録音も大変で、ものすごい数のテイクが重ねられたと記録されています。
一度も聞いたことがなく、これを読んだだけだと、なんだかグチャグチャごちゃごちゃなイメージなんですが、聞いてみると、えらいスッキリと仕上がっています。
また、次々と変わる場面ごとのジョンの歌い分けが素晴らしく、加えてアレンジが天才的で、聞き終わると「ビートルズ恐るべし」となるわけです。
超難解な歌詞:セクションごとの解説
1. 最初のセクション:視覚的イメージ
歌詞の内容は視覚的で抽象的なイメージが中心です。
**
- “She’s not a girl who misses much”
こののフレーズは「彼女は何も見逃さない女の子ではない」だけれど、それだと何のことかわかりません。
解釈としては、つまり、彼女は非常に鋭敏で、周りの出来事やチャンス、細かいことをよく理解し、見逃さない性格だということを示しています。
逆に言うと、彼女は注意深く、鋭い洞察力を持っていることを表現しています。
**
- “She’s well acquainted with the touch of the velvet hand / Like a lizard on a window pane”
前半は「「彼女はベルベットのように滑らかな手の感触をよく知っている」という意味でここはまだまともですね。
後半は「(そういう彼女が)まるで窓硝子にへばりつくトカゲのようだ」と言っており、これまたよくわからない。
想像ですが、「彼女が「ベルベットの手の感触」に対して強く執着している、またはそれに依存している」ということを象徴しているかもしれません。
**
- “A soap impression of his wife which he ate / And donated to the National Trust”
前半部分は「彼が食べた妻の石鹸の印象」となって完全イミフ。”A soap impression”は「石鹸でできた姿(形or彫刻)」ぐらいが適切な訳で「彼が食べた、妻の形をした石鹸」となります。
後半は「(前半の)石鹸彫刻をthe National Trustに寄付した」ですが、ますます理解不能になるでしょう?
一つの解釈ですが、意図的に無意味さや混乱を強調している可能性があります。
National Trustは、英国の歴史的建造物や自然環境を保護するための団体ですが、保護されるべきものが本当に価値のあるものかどうかを問いかける皮肉なコメントとして解釈することもできます。
それに、石鹸彫刻のような儚く消えてしまうものを寄付することは、価値の曖昧さや矛盾を表しているかもしれません。
ジョンの頭はドラッグでラリってたんでしょうね。幻覚を言葉にしたのかもしれません。
2. 中間セクション:個人的な経験
歌詞の内容や個人的な経験や感情が描かれているのでしょうか。
ここでも引き続き、ドラッグの影響大です。
**
- “The man in the crowd with the multicoloured mirrors / On his hobnail boots.”
意味は「群衆の中にいる男がいて、彼は、その鋲付きブーツに多彩な鏡をつけている」で、サイケデリック感満載です。
“The man in the crowd“だけなら「群衆に埋もれている一人」なのですが、それに続くフレーズが特別感を出しています。
“hobnail boots“とは、靴底に鋲を打ち付けて補強されたブーツのことで、特に19世紀から20世紀前半にかけての英国で労働者や兵士がよく使用していました。
しかし、その鋲付きブーツに関して”with the multicoloured mirrors“と補足されています。
小さなキラキラ反射するプラスチックの鏡のようなものがたくさんついているのであれば、伝統的な鋲付きブーツではなく、ファッショナブルな若者のブーツだったかもしれません。
ジョンは、典型的なサイケデリックな表現で現実と幻想の境界を曖昧にしつつ、彼が普通ではなく、何らかの形で世界を変える能力を持っている、または周囲の人々に影響を与える存在であることを示唆しています。
**
- “Lying with his eyes while his hands are busy / Working overtime.”
“Lying with his eyes” これは「本心を隠している」という意味です。
“his hands are busy / Working overtime“は「彼の手がとんでもなく忙しく仕事をしている」という意味です。
ジョンがどういう状況を想定していたのかはわかりませんが、私はこの歌詞を読んで「イギリスの底辺社会で働く労働者が感情を隠し、ただ黙々と手を動かしている状況」を想像しました。
**
- “Mother Superior jump the gun”
マザー・スーペリアとはカトリック教会の修道院長(女子修道院の上級者)を指します。
このフレーズは、修道院長が通常の手続きを急いで進める、あるいは先走ることを意味しており、焦りや急ぎの象徴として使われています。
急いでいる理由も含めた、このフレーズの一つの解釈ですが、
修道院長は自分が負うべき責任やプレッシャーに押しつぶされるようにして、段々と焦りを感じ、最終的に過剰な行動(jump the gun)に走ることになります。
ジョン・レノンがこの状態を批判していると考えると、彼が批判しているのは、過度なプレッシャーが人を非合理的な行動に駆り立てることや、権威者がその責任感ゆえに間違った判断をしてしまうことへの警鐘かもしれません。
3. 最後のセクション:銃のメタファー
歌詞の内容は銃のメタファーが強調され、タイトルのフレーズ「幸福は温かい銃」が繰り返されます。
「幸福を感じる瞬間」と「銃の引き金を引く瞬間」が強調・象徴的に対比されています。
**
- “When I hold you in my arms / And I feel my finger on your trigger”
この文は、音節のバランスやリズムや流れを整えるために”and”を入れてますが、実質的には”When A, B.”構文です。
直訳すると「君を腕に抱いている時、僕は君の鼓動(欲望)を指に感じる」となります。
ここで重要なのが、”feel my finger on your trigger“という部分です。
実は「銃の引き金に指を置く感触」を指しており、物理的な感覚としての引き金に触れることを表現しているという側面があるのです。
そして、銃の引き金を引く瞬間の緊張感と、愛する人を抱きしめる瞬間の感情を重ね合わせ、銃が持つ魅力や危険性を皮肉っています。
**
- “Bang, bang, shoot, shoot”
繰り返されるコーラスフレーズで、銃の発射音を模倣し、銃社会の暴力性を強調している。このフレーズが放送禁止の一因になりました。
当時のイギリスメディアは、特に過激な内容や暴力的なイメージを連想させる表現が厳しく規制されていました。
このバックコーラスは、銃の発射音を模倣しており、リスナーに強烈な印象を与えるため、それが暴力を連想させるものとして受け取られた可能性があります。
バンされたもう一つの可能性としては、銃の発射音を模倣する表現と同時に、性行為や性的興奮を連想させるような内容が含まれていると見なされたことだった可能性も十分あります。
社会的背景と影響
銃文化への風刺
ジョン・レノンは、アメリカの銃文化に対して強い批判を持っていました。
この曲は、銃を持つことが幸福とされる文化に対する強烈な皮肉を込めています。
特に、銃が日常生活の一部として受け入れられている現実に対する批判が強調されています。
ジョンのインタビューと説明
ジョンは、この曲のタイトルが「アメリカン・ライフルマン」という雑誌に掲載された記事のタイトルから取られていると説明しています。
そして彼は、そのタイトルを「とても恐ろしい考え」として受け取り、それが曲のインスピレーションになったと述べています。
一方ジョンは、この曲を「セックスや銃に対する風刺的な視点を含んでいる」とも説明しており、銃がもたらす暴力と性的快楽が結びつけられることへの批判も含まれていることが示唆されています。
ドラッグの影響
また、曲の中にはドラッグに対する言及も含まれています。
ジョン・レノン自身がドラッグを使用していたこともあり、この曲の一部にはドラッグ体験から得たイメージが反映されています。
先のあげた歌詞と訳を見ても頭がぶっ飛んでいたのは明らかです。
ジョンとドラッグ
ジョン自身の証言:ジョンは公にLSDなどのドラッグを使用していたことを認めており、その影響が彼の音楽や歌詞に反映されていることを語っています。
彼は特に「The White Album」の制作時にドラッグの影響があったと述べています。
- まともに「必要だ」:「I need a fix」という行があります。”fix”は麻薬を指すスラングです。
- 薬が切れた時の状態を表現:続いて「cause I’m going down」。これは「気分が悪くなる」という意味で、ドラッグの切れ目に感じる不快な状態や精神的な低迷を示しています。
しかし、これだけ非難を受けるような内容を露骨に直接的に表現しているのに、それでも社会から見放されず抹消されなかったのは、私にとってはこっちのほうが衝撃的です。
それどころか、別の曲も相当やばいのが入っているのに、10枚目のLP「THE BEATLES」通称「WHITE ALBUM」は売れに売れたのでした。
You Never Give Me Your Money – 内部崩壊への失望と苛立ち
この記事最後に紹介するのは”You Never Give Me Your Money“です。
今までの曲は、外部に対しての皮肉や批判を歌詞に込めてたのですが、この曲は真逆で、自分たち自身の財政問題や人間関係に関するフラストレーションを歌っています。
ビートルズの最後のアルバム”Abbey Road“に収められています。
この頃の4人の関係は最悪とされ、音楽雑誌にも始終不和説が掲載されていて、当時高校生だった私は「なんとか解散だけは避けてくれ」と祈るような気持ちでした。
にも関わらず、”Abbey Road“はビートルズの最高傑作だと多くのメディアに称賛されています。(アルバムの売上としては3位)
さて、ポールはフラストレーションをどんなふうに皮肉って昇華させたのでしょうか?
その話をする前に、、、
ブライアン・エプスタインの死が招いた深刻な問題
ビートルズの初期の成功には、マネージャーであるブライアン・エプスタインの尽力が大きな役割を果たしました。
ところが、そのエプスタインが、1967年にカリソプロドールという筋弛緩剤と、シークナールという睡眠薬の過剰摂取によって急逝しました。
エプスタインの死が、ビートルズの運命を大きく変えてしまったのです。
財政管理がうまくゆかなくなり意味のないロスが増え、活動マネジメントも4人が納得ゆくような内容ではなくなってきてギクシャクしていきます。
では、その苛立ちが歌詞にどう表現されているのかを、歌詞中の幾つかのフレーズを紹介しつつ解説します。
“You never give me your money / You only give me your funny paper”
“your funny paper“とは、価値のない紙切れや無価値な約束を指します。
ここでの皮肉は、実際に欲しい現金や安定した収入が得られず、代わりに無意味な約束や契約書しかもらえないことを批判しています。
このフレーズは、ビートルズがマネージャーのアラン・クレインとの財政的な問題や、アップル・コア(ビートルズが設立した多角的企業)の財政管理の問題を反映し、同時にポールの苛立ちも感じます。
Out of college, money spent / See no future, pay no rent
このフレーズは、将来に対する不安や経済的なプレッシャーを表現しています。
「大学を出た後にお金を使い果たし、将来が見えず家賃も払えない」状態を描いています。
ビートルズは、成功を収めた後も多くの財政的問題に直面しており、これは彼らのフラストレーションと失望感を反映しています。
Step on the gas and wipe that tear away
“Step on the gas“は「アクセルを踏む」という意味です。
車を加速させるためにアクセルを踏むことを指しますが、ここでは「急いで前に進む」または「問題を解決しようと急ぐ」という比喩的な意味で使われています。
というよりも寧ろ、現実から逃避しようとする姿勢を表しています。
ビートルズのメンバーが活動の混乱や問題を解決するのではなく、ただその場から急いで逃げようとする皮肉が込められています。
“wipe that tear away“は「その涙を拭き取る」という意味です。
直接的には、悲しみや不満を抑える、涙を流さないようにするというニュアンスが含まれています。
このフレーズは、表面的には「泣くのをやめて前向きに進もう」として理解できますが、実際には問題を解決する代わりに、単にそれを無視して感情を押し殺すという皮肉なニュアンスが込められています。
ビートルズのメンバーが現実的な問題を解決することなく、単に感情を抑えて前に進もうとする姿勢を批判しています。
One sweet dream / Pick up the bags and get in the limousine
“One sweet dream“は直訳すると「一つの甘い夢」とですね。
つまり、ビートルズがかつて夢見ていた成功や栄光を象徴していますが、その夢が現実と合わなくなってきたことを示唆しています。
ビートルズのメンバーが成功を夢見ていた頃の理想が、現実の問題に直面していることを反映しています。
“Pick up the bags and get in the limousineは「荷物をまとめてリムジンに乗り込む」という意味で、これは、すぐに現場を離れる準備をすることを指します。
現実から逃避しようとする姿勢を表しているんですね。
ビートルズが現実的な問題に直面しているが、その問題を解決する代わりに、物理的にその場を離れることで解決しようとしている皮肉が込められています。
**
ビートルズがブライアン・エプスタインの死後に直面した活動マネジメントの混乱や、その混乱から逃れようとする姿勢が言葉を変えて述べられていましたね。
これらのフレーズに込められた皮肉や批判を理解するためには、単に歌詞を直訳するだけでなく、背景にある状況やメンバーの心情を理解する必要があります。
が、「言うは易し」で、ま〜ぁ半端ない時間がかかりました。
【集大成】ビートルズの楽曲に込められた皮肉と批判
ビートルズの音楽は、単なるポップソングの枠を超えて、深い意味と多層的なメッセージを持つものです。
彼らの楽曲には、社会や個人のフラストレーション、皮肉、批判が巧みに織り込まれており、それが彼らの音楽を時代を超えた不朽のものにしています。
皮肉と批判の表現
ビートルズの楽曲には、表面的には肯定的に見えるメッセージが、実際には皮肉や風刺を込めたものが多く存在します。
たとえば、”Happiness is a Warm Gun“では、銃を持つことの幸福を歌うように見せかけながら、実際にはアメリカの銃社会を痛烈に風刺していましたね。
このように、彼らの音楽には聴き手を一瞬戸惑わせ、再考を促す要素が含まれています。
内部分裂とフラストレーション
特に後期のビートルズの楽曲には、メンバー間の緊張やフラストレーションが色濃く反映されています。
“You Never Give Me Your Money“は、バンド内の経済的問題や管理の混乱を表現していました。
ポール・マッカートニーは、この曲で他のメンバーに対する不満を表明しつつも、ビートルズとしての音楽制作を続ける姿勢を示しています。
この矛盾した感情が、彼らの音楽に深みを与えています。
文化的背景の影響
ビートルズの楽曲は、1960年代の社会情勢やカウンターカルチャー、ドラッグ文化といった当時の文化的背景を深く反映しています。
これらの背景を知ることで、彼らの楽曲に込められたメッセージがより明確になります。
例えば、今回は取り上げませんでしたが、”Lucy in the Sky with Diamonds“はサイケデリックな世界観を描いており、当時のドラッグ文化との関連がしばしば議論の対象となっています。
音楽的革新とその影響
ビートルズは、音楽的な革新を追求しながら、自らのフラストレーションや社会批判を表現してきました。
彼らの楽曲は、単なる娯楽としてだけでなく、時代の精神を映し出すものとしても機能しています。
彼らの音楽が不朽のものとなっているのは、このような多層的なメッセージ性と、深い社会的洞察が込められているからです。
終わりに
ビートルズの音楽に込められた皮肉や批判、フラストレーションを理解することで、彼らの楽曲がいかに豊かな意味を持つかを再認識することができました。
彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、深く考察し、背景を知ることで、より一層その魅力を味わうことができます。
この記事が、ビートルズの音楽をさらに楽しむための一助となれば幸いです。








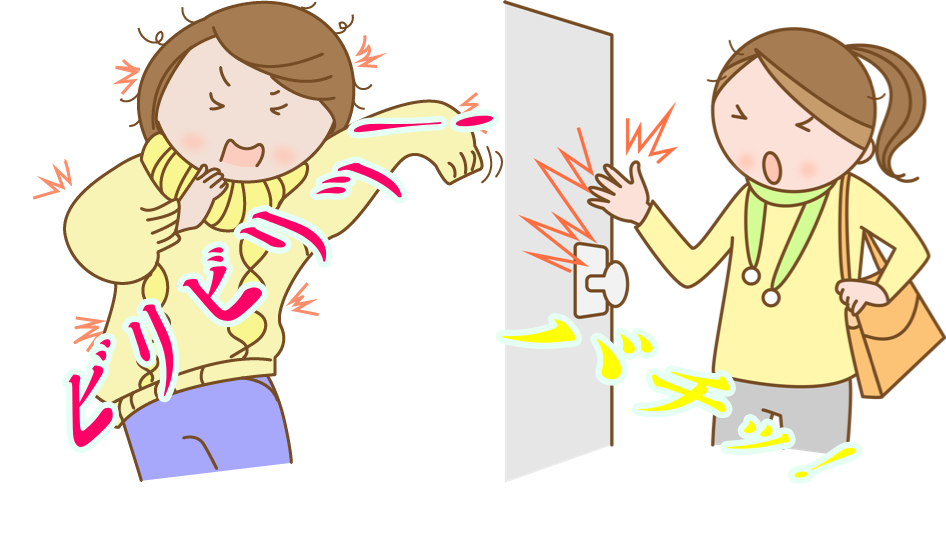



それは、私自身が青春時代にビートルズから語れないほど大きな影響を受けたからです。